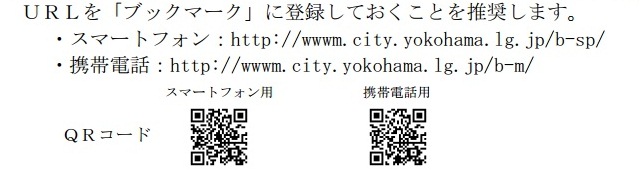横浜市においても、東日本大震災から1年以上が経過し、津波避難対策や帰宅困難者対策など、取り組みが進められています。
津波避難対策に関しては、現在公共施設や民間施設との連携のもと、「津波避難施設」の指定が進められています。この「津波避難施設」は、「津波発生時における施設等の提供協力に関する協定書」というものを横浜市と施設が締結し、津波発生時に施設を開放することで、津波避難者を受け入れるものです。4月9日の発表段階では、民間施設27件、公共施設70件の合計97件が指定され、一部施設では「津波避難施設」の表示が掲出され、現在も交渉作業が続いているということです。
横浜市役所にも「津波避難施設」の標示が掲示されていますので、昨日(5月8日)、人の出入りを見守る守衛の方や、受付の方に、この掲示に対する認識と、発災時の役割について確認をしました。すると、掲示されたのは知っていても、発災時に具体的に何をすれば良いのかは分からない、という回答が返ってきました。そこで本日(5月9日)消防局の担当者に確認をとったところ、マニュアルの策定中であり、完成次第徹底していく、という旨の回答がありました。とはいえ、本庁舎での話です。迅速な対応が求められますが、お粗末と言わざるを得ません。
3月14日に開かれた常任委員会などを通じて、この津波避難施設や、赤レンガパークや山下公園に設置された「津波避難情報板」(P4)について、消防局と議論を行ってきました。ポイントは、「案内をする人が居なくても避難できるかどうか」です。
消防局のHPを見れば、どこのビルが指定されていて、どの位置に津波避難施設あるのかが分かるようになっています。でも発災時は、スマートフォンなどで確認する余裕など当然ありません。特に、赤レンガパークや山下公園などは、市外からの来街者も多く、日によっては数万人から10万人以上の方が訪れる地域です。そうした中で、70件の公共施設には掲出が完了しているということですが、民間施設に関しては一部でのみ掲出となっています。普段掲出していない施設では、津波警報が発表された際には掲出することとなっていると言います。しかしながら、いつ、どのような規模で地震が起きるか、津波が発生するかは予測ができません。万が一の時に、掲出する余裕があるのか、誰が掲出するかマニュアルが徹底されるかなど課題もあります。掲出をするために逃げ遅れる、なんて事があっては本末転倒になります。帰宅困難者支援としては、9都県市でコンビニやファミレスとの協定が進み、災害時帰宅支援ステーションのステッカーの掲示がされています。帰宅支援ももちろん重要ですが、津波避難は一刻を争うことです。いざ発災すれば、避難する方々は、横浜市と協定を結んでいようがいまいが関係なく、最寄りの高いビルに避難することも十分想定されます。中には安全ではないビルもあるでしょう。土地勘のない人でも、迅速に、安全な場所に避難できるように、公共、民間ともにできるだけ多くの施設を指定し、常時掲出することが重要だと考え、消防局に対策を求めてきました。
また津波避難情報板については、5か所6枚(赤レンガパーク・象の鼻パーク・日本丸メモリアルパーク・山下公園 2 か所・臨港パーク)にとどまります。津波を直接受ける場所であり、来街者が多く集まる場所でもあります。とはいえ、浸水域はより広範囲に及びますし、何より数万人の方々が順番に6枚の情報板を見てから逃げる、ということも考えられません。関内ホールや横浜スタジアムなどのように、直接海に面していなくても、収容力がある施設もあります。そうした場所から避難する方々を、どうやって安全な場所に誘導するのか。横浜市の沿岸区域では、街路灯などに7,700か所、海抜標示がされています。その場所が海抜○mであるということが分かります。しかしながら、どこに逃げれば安全なのかは分かりません。右に行けば避難施設があるのか、左に行けば高台なのか。必要なのは、発災時に走ったりして逃げながらでも、どこに行けば安全なのかが分かる対策だと考えます。そのためには、通りの角ごとに矢印で避難経路を示すような案内板が必要ではないか、ということも提案を行ってきています。東日本大震災の被災地の一部は、これまでも何度も津波の被害を受けた地域でもありました。私が訪れた宮城県の七ヶ浜もその1つです。過去の経験から、道路の角などには避難場所の方向と距離を示す案内板が立てられていました。それでも亡くなられた方が、沢山いらっしゃったのです。
帰宅困難者対策でも同じことを言い続けています。国道などの大きな道を、数時間かけて東京、川崎、横浜と歩いて帰られた「帰宅困難者」が大量に発生しました。駅で滞留した人が滞在する、一時滞在施設の指定も行われてきました。駅との協力も行われ、駅員の方が誘導を行うことにもなってきています。とはいえ、通勤時や帰宅時など、駅によっては数千、数万の方が利用されます。そうした時に、駅員の方だけでは十分に案内・誘導しきれない事もあり得ます。そういう場合を想定して、駅構内や出口付近などに、案内板が必要なのではないか。
地震発生時、津波発生時に向けてマニュアルを作成し、役割を決め、訓練を行うことはもちろん重要です。とはいえ、横浜市の沿岸区域のように来街者が多く集まるような場所では、「誰か」が動かないと成立しない対策では不十分であると考えています。
<参考>横浜市帰宅困難者一時滞在施設検索システム
発災時に、どこに施設があり、どこが空いているかなどを、携帯電話・スマートフォンで検索堪能なシステムが運用されています。
Post comment
RECENT POST
- 2024.07.19
子どもの意見表明機会の確保に取り組む、堺市のいじめ対策。 - 2024.07.18
大阪大学図書館と市立図書館の一体運営。箕面市立船場図書館 - 2024.06.22
里親支援のフォスタリング機関「さくらみらい」視察報告。 - 2024.04.15
市長部局と条例で、子どもをいじめから守る。寝屋川市いじめ対策視察。 - 2024.04.13
不登校生徒が通う学びの多様化学校。大阪市立心和中学校視察報告。
RELATED POST
- 2024.07.18
大阪大学図書館と市立図書館の一体運営。箕面市立船場図書館 - 2024.03.21
山下ふ頭再開発と、市民参加機会の充実について。常任委員会から。 - 2024.03.18
図書館の充実、財政情報見える化。R6財政局予算。 - 2024.03.17
共通投票所の駅周辺、商業施設への設置を提案。R6選挙管理委員会予算。