以前から、「事業評価会議」の問題を指摘してきましたが、平成24年度予算案において、事業の休止の方針が示されました。とはいっても、25年度から再開予定ですが。今回の休止理由は、市民の参加や関心が低かったため、方法を見直すというものです。「見直し」と言えば聞こえは良いですが、どのように見直すかが重要です。「見直した結果、会議予算を増額しました」では、全く駄目です。
事業評価会議の目的には「市民の皆様が直接参加し、公開の場で議論を行うことにより、多様化する市民ニーズに的確に対応した事業を効果的かつ効率的に実施し、透明性、信頼性の高い市政を確立する」とあります。一見すると非常に魅力的なフレーズが並んでいます。問題は、それを実現するためには、どんな手段が最適なのかです。
直接参加という目的に関しては、タウンミーティングを開催して議論するとか、パブリックコメントという制度を用いるとか、他にも流山市のようなパブリック・インボルブメントという手法や、区民会議、泉区で行われている地域協議会など、方法はいくつもあります。いずれも公開で行われますし、市民ニーズを把握するための取組でもあります。
事業の見直しといえば、事業仕分けもあります。事業仕分けは、行政に精通している行政の外部の識者・経験者が、仕分け人として事業の要・不要を仕分けるものですが、近年は無作為で選ばれた市民が「市民判定人」として、仕分け人の議論を聞き最終結論を出す、という方法も増えています。
また、透明性、信頼性の確保も、ただ公開の場で議論すれば透明なのではなく、その場で導き出された結論が、そのまま実行されてこそ透明で信頼できるプロセスとなります。
色々書きましたが、改めて事業評価会議を振り返ると、「直接参加」を謳っていても、そもそも事業評価会議が意思決定の場ではないので、意見を直接伝えている場にすぎません。結局「議論」にも程遠く、ファシリテーターが全員に発言を促し、市民の方が圧倒的に情報が少なかったあの場では、「公開の場で職員へ質問」が行われただけです。何より、24枠あった公募市民枠への応募が32名だけ。会議の傍聴者が105名だけ。インターネット中継の同時アクセス数は50~110件。と、当局も認める通り、市民の参加・関心が非常に低いものでした(参考PDF)。
今回の実施結果をみて、事業の見直しを決定したことは評価します。また25年度に向けて根本的に見直しを行い、そのために参加された公募市民の方々にも意見を聞くということなので、その点も評価しています。内容は良くありませんでしたが、「事業評価会議」を用いて、事業の効果や効率性を議論をし見直しを図ろうとしている目的そのものも、評価しています。
市民の参加や、市民への公開、市民との議論、といったことは、非常に重要であると考えます。今後、市民参加での事業の見直しを行っていくのであれば、目的と手段を明確に切り分けながら、既存の枠組みにとらわれずに、「効果的かつ効率的に実施」できる手法を議論し、用いてほしいと思います。
Post comment
RECENT POST
- 2026.01.21
京都市会のペーパーレス化と通年議会。視察報告。 - 2026.01.19
神戸市会のペーパーレス化と、議会制度改革。議員の宣誓制度も。 - 2026.01.08
山内図書館のリノベーションと、市民の意見と利用しやすさ。 - 2026.01.07
定員超過と長期化という横浜市一時保護所の問題。里親支援の充実。 - 2025.12.29
新横浜の大型図書館と、ブックス&ラウンジ。図書館ビジョンの推進。
RELATED POST
- 2026.01.08
山内図書館のリノベーションと、市民の意見と利用しやすさ。 - 2026.01.07
定員超過と長期化という横浜市一時保護所の問題。里親支援の充実。 - 2025.12.29
新横浜の大型図書館と、ブックス&ラウンジ。図書館ビジョンの推進。 - 2025.09.02
横浜市教育職員等による児童生徒性暴力等の防止について。常任委員会。

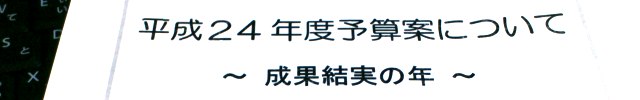



Comments 2
あのパフォーマンスだった民主の「事業仕訳」と今回の「事業評価」なる不可思議な代物を、もっと議会用語でなく、日常用語で報告してくれると一般の方は分かりやすいのでは・・・・と思います。
それぞれの「専門用語」に解説下線を入れているのは歓迎ですが、文中で分かりやすく
問題点が簡単に浮彫りされる表現を期待します。
僕は理解できましたが。
確かにおっしゃる通りですね。
できるだけ分かりやすく表現できるよう、取り組みます。